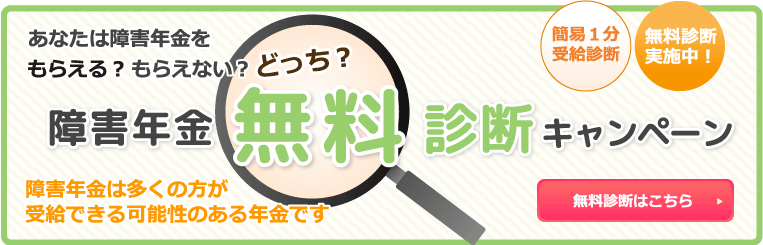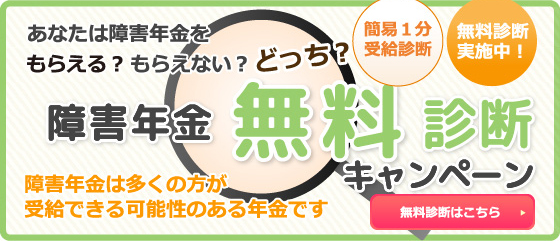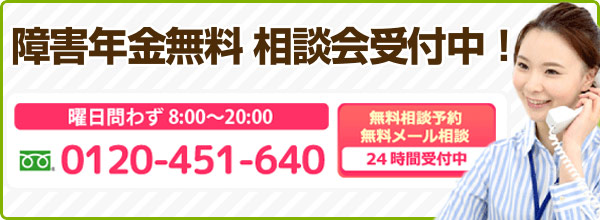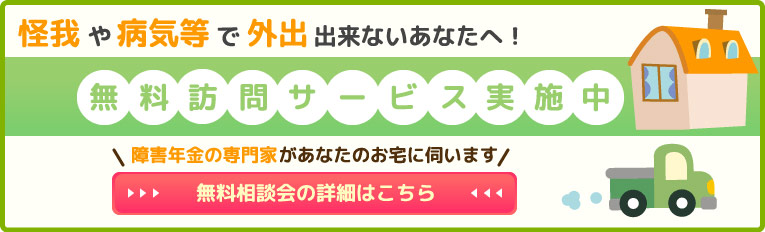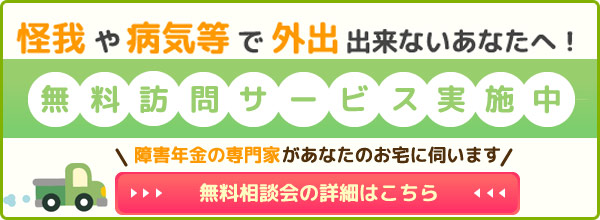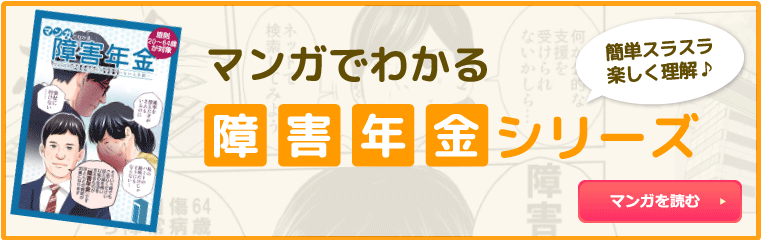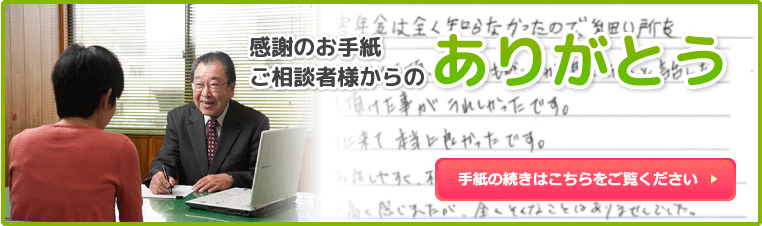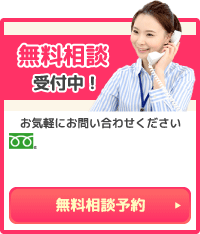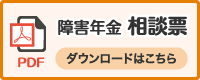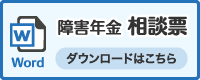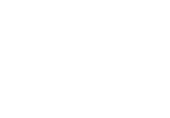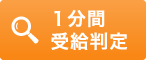障害年金の不支給率・地域差の実態徹底解説|障害内容別の対策を網羅
本記事では、障害年金の不支給率と地域差の実態について詳しく解説し、どのようなケースで不支給が発生しやすいのか、また地域差の背景には何があるのかを探ります。
障害内容別の不支給率や、対処法・不服申立ての方法を網羅的に取り上げることで、より適切な受給に向けたヒントを提供します。
障害年金の審査基準は一見すると全国で平等に適用されているように思われますが、実際には地域や障害の種類によって認定結果にばらつきが生じています。
特に精神障害や知的障害は不支給率が高い傾向があり、過去の調査結果でも顕著な地域差が指摘されています。
本記事を通じて、障害内容別の不支給リスクや地域差が生じる要因、そして不支給の場合の対処法を総合的に学ぶことで、今後の申請や再審査手続きに備えていただければと思います。
複雑な制度を理解し、不支給を回避するための具体的なステップを一緒に確認していきましょう。
障害年金の全体像と不支給率の背景
まずは障害年金の仕組みと、なぜ不支給が生じるのか、その背景を整理します。
障害年金は、公的年金制度の中で障害を負った人の生活を支える重要なセーフティネットです。
しかし、障害の程度や初診日といった要件を厳密に満たさない場合や、書類不備などの理由で不支給となるケースも少なくありません。
制度の複雑さに加えて、医療機関や自治体の対応にも差があるため、申請者には十分な情報収集が求められます。
そもそも障害年金の認定基準は、身体障害・精神障害・知的障害など、多様な障害特性を踏まえる形で作られています。
ただし、実際の審査では障害の重症度を客観的に示す判断材料が不十分だったり、医学的所見が医師によって異なったりする場合もあり、そこから不支給トラブルが生まれることもあります。
さらに、過去には自治体や年金事務所による運用の違いが大きな問題となり、同じ程度の障害でも地域ごとに認定結果が異なるという事例が報告されました。
不支給率の高止まりや地域差の発生には、制度の構造上の課題や運用の不統一が影響していると言えるでしょう。
不支給の現状:統計データから見る割合
公的機関が公表したデータによれば、障害年金の不支給率は障害の種類によって変化が大きいとされています。
特に精神障害や知的障害の場合は約6~7割以上が審査対象となっており、このうち一定数が実際に不支給と判断される事例が多い傾向にあります。
2015年には障害基礎年金の認定率に関する調査結果が発表され、都道府県ごとに不支給になった割合に大きな開きがあることが確認されました。
例えば精神障害・知的障害の審査では、日常生活能力評価をどう判断するかによって認定結果が大きく左右されるという指摘もありました。
身体障害の場合は、肢体機能の程度や発症状況がはっきりしているケースが多い一方、不支給率が地域差の影響を受けにくいとされています。
とはいえ同じ身体障害でも、診断書の記載方法や初診日書類の不備によって受給可否が分かれることがあるので要注意です。
不支給が生じる要因と制度の課題
不支給が生じる最大の要因としては、医療機関が発行する診断書の内容が慢性的に不十分であることが挙げられます。
診断書には障害の程度や日常生活への影響度を的確に記載する必要があるにもかかわらず、医師の理解不足や申請者とのコミュニケーション不足によって、不支給につながる事例が後を絶ちません。
また、制度自体が複雑であることも大きな課題です。
初診日の証明書類や病歴・就労状況等申立書など、多岐にわたる書類を適切に整えられないと認定が下りにくくなる可能性があります。
さらに障害年金の審査では、障害の原因となった疾患の経過だけでなく、その後の状態変化も含めて総合的に判断します。
これらの点を見ると、申請者や医療機関のみならず、認定医側の専門性や実務経験も認定の結論を左右していることがわかります。
地域や審査担当者ごとに基準の捉え方に温度差がある場合、同じ障害程度でも不支給になる確率が変わりうるため、制度運用のさらなる統一化が求められています。
障害内容別の不支給率:身体・精神・知的障害ごとの傾向
障害の種類(身体・精神・知的)の違いによって不支給率にはどのような差があるのでしょうか。
障害内容が異なると、医学的な認定基準や日常生活への影響度の評価も変わってきます。
そのため、身体障害・精神障害・知的障害ごとに不支給率や認定基準の解釈が異なり、取得できる情報の質にも差が生じる可能性があります。
一般的には身体障害は診断や検査結果が比較的明確であり、精神障害や知的障害は症状・程度を客観的に把握しにくいと言われています。
特に精神・知的障害は審査過程で主観的評価を要する部分が多く、不支給となりやすい要因にも繋がっているのです。
ここでは、障害年金申請時の不支給を防ぐために、それぞれの障害特性をふまえたポイントを具体的に確認していきましょう。
身体障害における不支給率の特徴
身体障害の中でも、肢体の障害は医師による客観的な検査データが整備されている場合が多いです。
レントゲンやMRIの結果、移動能力、握力や筋力低下の度合いなど、数値化できる指標があることで認定の精度は比較的高いといえます。
一方、内部障害(心臓や腎臓などの疾患)や外部障害(視覚・聴覚障害など)では、日常生活への支障度を正しく伝達できないと診断書に具体性が欠けてしまうことがあります。
結果として、障害の重さが正しく評価されずに不支給となるリスクもあるでしょう。
このように身体障害はデータに基づいた判断が行いやすい反面、書類の不備や診断書の書き方次第で不支給に転じる例があり、申請者側は事前の準備と医師との連携をしっかり行う必要があります。
精神障害・発達障害における不支給率と課題
精神障害や発達障害では、症状の変動が大きいことや外見からは障害の重さが理解しにくい場合が多く、不支給率が高い傾向があります。
特に審査時に、日常生活能力の評価が厳しめに判断されることが指摘されており、地域によって評価基準が統一されていないケースも見受けられます。
また、申請者本人が自らの障害の状態を正確に把握できない場合が多い点も、問題を複雑にします。
医師や支援機関との面談で症状を詳細に伝えきれず、結果的に診断書や申立書に実態が反映されないことが不支給につながる大きな要因です。
このため、あらかじめ支援者や専門家のアドバイスを受けつつ、日常生活で困っている事柄をメモし、診断書や申立書に具体的に落とし込む工夫が大切です。
正しい症状把握と書類作成プロセスが整えば、審査側も客観的に理解しやすくなり、不支給回避の可能性が高まります。
知的障害における不支給率の実情
知的障害の場合、IQスコアなどの客観的データがあるものの、日常生活でどの程度の支援を必要としているかの評価が大きなポイントになります。
知的障害を抱える本人や家族が、障害特性をどこまで正確に書類に反映できるかが鍵です。
また、軽度知的障害の場合は基準を満たさないと判断され、不支給となることが少なくありません。
外部からは障害の程度が把握しにくいケースも多いため、医師や関連機関による追加の客観的資料を準備することで認定につなげるケースがあります。
特に精神障害と合併している場合や発達障害を併発している場合は評価が複雑になり、さらなる不支給リスクが生じることもあります。
自分の障害特性に合った申請方法を知り、正確な証明書類をそろえることが重要です。
地域差はなぜ生まれる?過去の問題と現在の実情
地域によって認定率が異なる現象はなぜ起きるのか、歴史的経緯から最新の実情までを整理します。
障害年金の認定基準は国で定められているものの、実際の審査は地方の年金事務所や認定医によって行われます。
こうした仕組みに起因して、以前から地域格差が問題視されてきました。
特に、精神障害や知的障害の場合、どのように日常生活能力を評価するかで認定結果が大きく異なることが確認されています。
認定医の経験や考え方、地域の医療体制が評価基準の解釈に影響を与えている可能性が高いのです。
近年の取り組みにより制度改革が進んでいるものの、データの収集や公開はまだ十分とは言えず、依然として地域差は解消されきれていないのが現状です。
過去の障害年金地域格差問題の経緯
厚生労働省が地域差の存在を本格的に調査したのは2010年代に入ってからですが、実際にはその以前から「同じ障害でも地域によって認定結果が全く違う」というケースが指摘されていました。
特に精神障害や知的障害など、外見から重症度が判断しづらい障害において顕著でした。
2015年1月には詳しい調査結果が公表され、障害基礎年金の新規申請の約66.9%が精神障害・知的障害に関連しており、不支給割合の高い地域ではこれらの障害種別での不支給も大きい傾向があると報告されています。
調査では、判断基準が地域や担当者によって統一されていないことも問題視されました。
この地域格差問題を受けて、厚生労働省は認定基準の統一化と認定医の研修強化に着手しましたが、格差を完全に解消できたとは言えず、現在も部分的に差が残っています。
認定医や審査体制による差異
障害年金の審査は、認定医と呼ばれる専門の医師が書類の内容を確認し、総合的な判断を下します。
しかし、認定医自身の専門分野や経験、または地域での実務習慣などの影響を受け、同じ事例でも判定が異なるケースがありえます。
例えば精神科の臨床経験が豊富な認定医であれば、精神障害の症状を多面的に理解しやすく、結果として適切に認定される可能性が高まるかもしれません。
一方で、実績の少ない医師が審査に当たると、書類上の情報では障害の深刻度が伝わりにくく不支給に至るといった事態が起こり得ます。
また、審査体制自体も地域によって異なる場合があり、複数の認定医が集まって合議制で判断する地域と、個別に判断する地域とでは結論に違いが生じることが少なくありません。
現在の制度改革とガイドライン整備
現在、厚生労働省や日本年金機構では、地域格差を縮小するための改定・指針づくりを進めています。
認定医研修のカリキュラムの整備や、審査マニュアルの更新といった取り組みはその一環です。
実際に、新たなガイドラインでは精神障害や知的障害の評価手順がより詳細化し、主観的な評価を可能な限り排除する工夫が試みられています。
これにより、認定結果が地域ごとに極端に異なるという事態の防止が期待されています。
しかしながら、病院や医師との連携不足や、ガイドラインの具体的な運用方法が周知されないなどの課題も残っています。
引き続き、運用の迅速かつ適正な統一化が求められるでしょう。
等級判定ガイドラインの要点と適用対象
不支給を回避するためには、どのようにガイドラインが定められ、どの障害にどう適用されるかを理解することが重要です。
障害年金の等級判定は、障害の程度を1~3級に区分して認定する仕組みです。
近年では、この等級判定におけるガイドラインがより細かく設定され、申請者側にとってポイントがわかりやすくなってきました。
しかし、精神障害や知的障害など、重症度を定量化しづらい障害に対しては、まだ解釈にグレーゾーンが残っているのも事実です。
ここでは、ガイドライン上の注意点と適用される範囲を確認していきます。
正しいガイドラインの理解と、医療機関・支援機関との連携が、等級判定で不利益を被らないための第一歩となるでしょう。
精神障害への適用ポイント
精神障害の場合、診断書には病名だけでなく、どのような症状が日常生活や社会活動に支障を来しているかを具体的に書く必要があります。
ガイドラインでは、具体的な行動面での制限や、対人関係への影響度などを細かくチェックされます。
また、就労の有無については従来から注目されてきましたが、実際には就労できていても十分な職場環境の配慮があるケースや、実質的に業務ができない状態に近い場合などが考慮されるべきです。
ガイドライン上でも、就労の形態や勤務時間、同僚のサポート状況などを確認するよう指示されています。
こうした情報を具体的に盛り込むことで、審査医が障害の深刻度を適切に判断しやすくなり、不支給リスクを下げることにつながります。
知的障害・発達障害への適用ポイント
知的障害や発達障害の場合、IQなどの客観的評価指標だけでなく、生活の中で実際に生じている困難を明確に示すことがポイントです。
ガイドラインでも、学習能力やコミュニケーション能力、社会的適応能力などを複合的に評価することが求められています。
発達障害の場合は、特性が多岐にわたり、就労や対人関係に大きな制約が出る場合もあれば、うまくサポートを受けて生活できるケースもあります。
書類作成時には、本人の得意・不得意を具体的に記すことで、障害の程度を正しく伝えやすくなるでしょう。
さらに、未成年からの経過を把握できる資料があると、障害の継続性や深刻度を示すうえで非常に有用です。
学校の成績表や特別支援教育の履歴なども、可能な限り添付することが望まれます。
その他の傷病に対する留意事項
障害年金は、外傷や内臓疾患などさまざまな障害を対象としています。
ガイドラインはある程度包括的に作られていますが、それでも個別の病状や治療経過は多種多様で、書類上の説明が不足すると不支給になるケースが懸念されます。
また、症状が一時的に回復していると見られてしまうと、受給対象外と判断される可能性も否めません。
慢性的な影響が継続していることを証明するためにも、定期的に受診して医療記録を蓄積しておくことが重要です。
年金審査では、その時点での状態だけでなく、今後の経過や生活への影響度も考慮されます。
日常生活動作の制限度や社会的参加の状況を、できるだけ客観的資料で裏付けて申請することが望ましいでしょう。
不支給を防ぐための申請時の注意点
申請時の書類や提出方法に関する不備が、不支給や認定漏れを招くことも少なくありません。
意外なところで不支給リスクを高めてしまうのが、初診日の証明書類がそろわないケースや、診断書の記載漏れなどの書類不備です。
申請前に担当医や専門家と念入りにチェックしておくとよいでしょう。
また、病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、事実を規定の書式に落とし込む作業が複雑で、どうしても抜け漏れが生じがちです。
特に精神障害や知的障害では、本人が認識していない困難を周囲が気付いてあげる必要があります。
ここからは、申請時の各書類の重要点と、その整え方を詳しく見ていきます。
診断書の正しい記載依頼とチェック
診断書は障害年金の申請において最も重要と言っても過言ではありません。
医師が記載する項目には、障害の原因疾患、症状、合併症の有無、日常生活への影響等が含まれており、寸分違わず正確に書いてもらう必要があります。
とりわけ精神障害や知的障害では、医師と患者の間で主観的認識にズレが生じることが多いため、一緒に病院へ行って相談するか、医師に十分な時間を割いてもらうよう依頼するのが望ましいでしょう。
診断書の内容については、受け取ってから必ず確認する作業を怠らないことが大切です。
不備を見逃すと修正が難しくなり、結果的に審査に大きく影響してしまう可能性があります。
初診日の証明書類を揃えるコツ
障害年金の受給資格を得るうえで、初診日の特定は非常に重要なポイントです。
初診日がどこの医療機関だったのかを明確に証明する必要がありますが、カルテが廃棄されてしまったり、本人が転居を繰り返しているなどの理由で入手が難しいケースがあります。
もし初診日の証拠が得られない場合、受診状況等証明書の代替書類として、第三者証明や当時の健康保険証の記録など、可能な限りあらゆる角度から証明する手段を検討することが必要です。
こうした手続きをスムーズに進めるためにも、通院履歴や処方記録は念入りに保管しておくことが望まれます。
特に精神科や発達障害関連の通院記録は社会的な偏見から失念・廃棄されがちなので注意が必要です。
病歴・就労状況等申立書の適切な作成
病歴・就労状況等申立書は、障害の発生から現在に至るまでの経緯を時系列でまとめる重要な書類です。
身体障害だけでなく、精神障害や知的障害の場合でも、具体的にどのような症状や生活上の支障があったかを明記する必要があります。
また、就労状況や通院状況を記載する際は、具体的な業務内容や勤務時間、通院頻度などを可能な限り正確に書きましょう。
抽象的な表現に終始すると、審査側も状況を正しく把握できません。
この書類作成には時間がかかる場合が多いため、早めに準備を始め、必要に応じて支援機関や専門家のチェックを受けるとよいでしょう。
そうすることで、不服申立てをしなくても済むような質の高い申請書が完成します。
不支給となりやすいケースと事例
どのようなケースで不支給が発生しやすいのか、実例を交えながらチェックしましょう。
せっかく苦労して書類をそろえても、不支給となってしまうケースは少なくありません。
ここでは典型的なパターンを挙げ、不支給率を下げるために回避すべきポイントを整理します。
特に症状が安定していると見なされた場合や、提出書類に重大な欠陥がある場合には、不支給となるリスクが高まります。
誰もが当てはまる可能性があるため、事前に知識を得て対策を講じることが重要です。
以下では、よく見られる不支給パターンを具体的に確認し、改善策を探っていきましょう。
障害の程度が軽いと判断された場合
提出された診断書や病歴・就労状況等申立書などを総合的に見たうえで、医療的判断が「障害の程度は年金の等級に当てはまらない」となれば、不支給となります。
例えば精神障害でも、短時間のアルバイトができているというだけで障害が軽いと見なされることがあります。
もちろん、実際には就労可能な職場環境だけが整っているだけで、判断基準の等級が相当レベルに達している場合もあります。
しかし判断材料が書類に明示されないと、表面的な就労状況だけで「程度が軽い」とされかねません。
申請時には、生活上の困難がどのように就労や日常生活に影響を与えているかを、医師および支援者と連携して正確に伝えることが大切です。
書類不備や証明不足による認定漏れ
年度が変わって提出書類のフォーマットが新しくなったにもかかわらず、旧式の書式で提出してしまうケースや、必須項目の記載が漏れているケースは想像以上に多いです。
こうした不備があると、審査が進まずに不支給扱いとなってしまうことがあります。
また、意図せず証拠書類の期間が途切れてしまい、障害の継続性を示せなくなる場合もあります。
特に初診日の明確な証明がとれないと、申請そのものが認められないリスクが非常に高いです。
書類の作成と提出の段階で専門家や年金事務所の窓口に相談しておけば、こうした初歩的ミスはかなり防げます。
提出前にもう一度、チェックリストを活用して確認する習慣をつけましょう。
申請事実と実態の乖離で不支給となる例
診断書上は重度障害とされているが、実際には日常生活の一部を普通にこなせているといった乖離が明らかになると、不支給に至る可能性があります。
障害の特性上、日によって症状が大きく変わる場合もありますが、書類だけでは理解されにくい場合もあります。
特に精神障害の場合、医師の書き方と本人の申立書、周囲の証言が噛み合わないと不信感を生み出し、不支給リスクが急上昇することがあるので注意が必要です。
事前に担当医と相談し、本人の症状の変動を正確に反映させる工夫が求められます。
日常生活や就労の場面で撮った記録や、通院以外での支援機関とのやり取りの証拠があれば、実態を客観的に補完できます。
書面との矛盾をなくすために、生活の状況を隠さず明確に伝えることが重要です。
不支給後の対応策:不服申立ての具体的方法
不支給となっても、再審査の手続きを行うことで受給の可能性を取り戻せる場合があります。
いざ不支給の通知が届いてしまっても、そこで諦める必要はありません。
審査請求や再審査請求といった法的手続きを踏むことで、結果が覆る可能性があるのです。
ただし、不服申立ての手続きには期限や必要書類、専門的な知識が求められます。
失敗するとそのまま受給権が得られなくなることもあるため、しっかりとした準備が不可欠です。
ここでは、不服申立ての流れや専門家の関わり方、紛争解決の選択肢について解説していきます。
審査請求・再審査請求の流れ
障害年金の不支給通知を受け取ったら、まずは審査請求を行い、年金事務所や社会保険審査官へ再度審査してもらう手続きを取ります。
審査請求の期限は通知を受け取ってから3カ月以内と定められているため、早めの行動が大切です。
審査請求が認められなかった場合には、さらに再審査請求という手段があります。
これは社会保険審査会で行われるもので、こちらも期限は審査請求の棄却決定後2カ月以内と定められています。
これらの手続きでは、新たな証拠書類の提出や書面による主張を追加できるため、初回申請時の不備を補うチャンスでもあります。
弁護士・社労士へ相談するメリット
不服申立ては書類作成から手続き進行まで複雑なプロセスを伴います。
弁護士や社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談することで、必要書類の再整理や主張の組み立てを効率的に進められます。
特に障害年金に精通した社労士であれば、過去の事例や判例の知識を活かして、どのような書類を追加すれば審査官の理解を得やすいかを具体的にアドバイスしてくれます。
費用の面は避けて通れませんが、成功報酬型に対応している場合や無料相談を行っている専門家もいるため、まずは積極的に情報収集してみるとよいでしょう。
紛争解決手段の選択肢と注意点
通常は審査請求・再審査請求が障害年金の不服申立て手段となりますが、それでも認められない場合、一部の例外的なケースでは裁判に進む選択肢も存在します。
ただし、裁判は時間や費用がかかるため、ほかの方法がないか慎重に検討する必要があります。
また、裁判を検討する段階では弁護士と連携を深め、提出できる証拠書類の整理や、医師への追加意見書の依頼などを行っておくことが重要です。
必要に応じて専門医の鑑定を求められるケースもあります。
どの選択肢をとるにしても、まずは不支給の理由を的確に把握し、書類の不足分を補ったうえで再度申請するのが基本です。
目先の対応策だけに捉われず、全体のプロセスを見渡す視点が求められます。
地域差解消に向けた最新動向:専門家の視点
地域による審査基準の違いや認定医の差を是正するため、国や自治体の取り組みが進んでいます。
障害年金の地域差問題は、長年にわたって是正の必要性が指摘されてきました。
厚生労働省や日本年金機構は近年、積極的にデータの公開や認定医の研修制度の充実を進めています。
そこには医療機関や専門家団体との協力が欠かせないため、地域の社会福祉協議会や医師会とも連携し、情報共有の場が設けられる事例が増えています。
専門家の視点からは、こうした多方面での連携が地域格差の解消に重要な役割を果たすと考えられています。
ただし、ガイドラインの整備と周知が十分になされていない地域も依然として残っており、まだまだ課題は山積みです。
国によるデータ公開と認定医研修の強化
過去に問題視された認定率の地域差を減らすため、国は積極的にデータを公開し、どの地域でどの程度の差が生じているのかを明らかにしてきました。
これは医療関係者や一般市民からの意見を取り入れる上で大きな一歩と言えます。
同時に、認定医を対象とした研修内容の拡充が行われ、精神障害や知的障害を中心に、より屋根の下の評価基準が共有されつつあります。
これにより、従来よりも客観的かつ統一的な判断が期待されています。
ただし研修が実施されたからといって、すぐにすべての認定医が同じレベルの判断を下せるわけではありません。
研修後のフォローや実地での検証も不可欠な要素です。
地域格差是正に向けた取り組み事例
ある自治体では、障害年金に精通した社労士や医師、福祉関係者が協力して、申請サポート窓口を設置しています。
そこでは事前相談から書類確認、申請後のフォローアップまで一貫して支援を受けられる仕組みが整えられています。
また、医療機関同士が連携し、統一のフォーマットやオンラインシステムを使って診断書作成をサポートする動きも広がっています。
こうした事例は自治体によって規模や内容が異なりますが、地域格差を少しずつ和らげる方向に寄与していると言えるでしょう。
今後は他の自治体にも水平展開され、さらなる支援制度の充実が期待されます。
一部地域では既に成果が出始めており、専門家の間でも注目を集めています。
今後予想される法整備・施策と課題
障害年金の地域差を完全に解消するためには、さらなる法整備や国レベルでの取り組みが求められるでしょう。
たとえば、認定医や年金事務所の判断プロセスを徹底的に可視化し、外部監査を導入する試みが考えられます。
しかし、その一方で医療現場の負担増や機微情報の取り扱いなど、さまざまな課題も存在します。
法整備が進めば進むほど、書類の厳格化や手続きの煩雑化といった問題も浮上する可能性があります。
最終的には、申請者と社会全体の利益をどのように両立させるかが課題となります。
専門家からは、単なる基準の統一化だけでなく、障害の特性を踏まえた柔軟な運用体制の構築を求める意見が多く出ています。
まとめ|地域格差を踏まえた適切な受給を目指そう
障害年金の不支給率や地域差の原因を理解することで、より適切な受給を目指すことができます。
本記事で紹介した対策や不服申立ての方法を参考に、慎重かつ迅速に行動しましょう。
障害年金の制度は多くの人にとって頼りになる反面、審査基準や書類準備の難しさから不支給となるケースも少なくありません。
特に精神障害や知的障害では認定が不安定になりやすく、地域によって結果にばらつきが見られます。
しかし、最近は国や自治体の取り組みによりガイドラインや認定医研修が整備され、改善の兆しがあるのも事実です。
書類作成の段階から医療機関や支援者と連携し、先手を打って対策を講じることが大切になります。
不支給通知が届いた場合でも、審査請求や再審査請求などの手段を活用すれば、覆る可能性があります。
制度の最新動向や専門家のアドバイスを参考に、一歩ずつ着実に手続きを進めていきましょう。
「障害年金の不支給率・地域差の実態徹底解説|障害内容別の対策を網羅」の関連記事はこちら
- 知的障害での障害年金申請:知能指数・療育状況・就労状況・療育手帳所持はどう反映される?
- 50歳でADHDと診断された方が知るべき障害年金申請のポイント
- てんかんの認定要領と発作の頻度・重症度 ─ 抗てんかん薬・外科的治療による抑制まで徹底解説
- 広汎性発達障害・自閉症で障害年金を申請するときに押さえておくべきポイント
- 脳血管疾患による高次脳機能障害で障害年金を受給するためのポイントと注意点
- 統合失調症で障害年金を申請するための完全ガイド
- 双極性障害(Ⅰ型・Ⅱ型)で障害年金を申請する際の全体像
- 神経症(パニック障害)で障害年金を申請する際のポイントと注意点
- うつ病(気分障害)で障害年金を申請する際の留意点【症状・処方薬も解説】
- 感音性難聴で障害年金を受給するための完全ガイド
- 障害年金と傷病手当金の併給調整
- 障害年金のメリットからデメリットまで徹底解説!
- 障害年金診断書における精神の「日常生活能力の判定」とは
- 障害年金と労災保険の併給調整とは?~知っておきたい留意点と手続き~
- 精神障害年金を受給しながら就労するための完全ガイド
- 交通事故における障害年金と損害賠償の調整完全ガイド
- 障害年金の不支給率・地域差の実態徹底解説|障害内容別の対策を網羅
- 精神疾患の方の自立支援医療の申請ポイントを徹底解説
- 自己破産申請と年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)受給の留意点
- 生活保護受給中の障害年金認定日(遡及)請求で押さえておきたいポイント




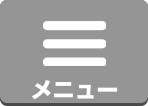
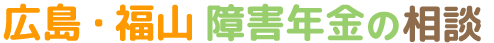
 0120-451-640
0120-451-640