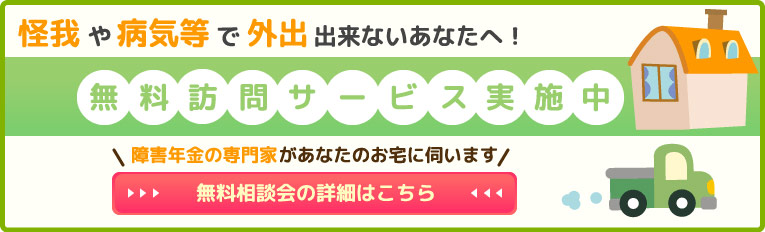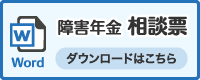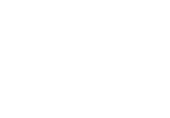受診状況等証明書が取れないときの初診日証明|「一定期間に初診日があること」で認めてもらう方法
障害年金の請求では「初診日」を証明できるかどうかが、受給可否を左右します。原則は初診の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらうことですが、廃院やカルテ破棄などで取得できないケースも少なくありません。
本記事では、受診状況等証明書が取れないときに使える代替手段と、日付が特定できなくても「一定期間に初診日があること」を根拠に認めてもらうための考え方・実務ポイントを整理します。提出書類同士の整合性チェックまで含め、申請前にやるべきことを時系列で分かる構成にしています。
受診状況等証明書とは
受診状況等証明書は、障害年金請求における初診日証明の基本資料であり、初診の医療機関が「いつ・どの傷病で受診したか」を証明するために用いられます。
障害年金では、原則として「初めて医療機関を受診した日」を初診日として扱い、その日付を公的書類で示す必要があります。その中心になるのが受診状況等証明書です。
証明書には、初診日だけでなく、初診時の傷病名、診療科、転帰などが整理されます。後から病名が変わった場合でも、当時の主訴や診断名が分かると、請求傷病とのつながりを説明しやすくなります。
実務上は、証明書に何を根拠に記載したかも重要です。カルテがなくても、受付簿や会計記録、レセプト由来の受診記録などの残存データに基づいて一部記載してもらえる場合があり、取れないと決めつけない姿勢が初動として大切です。
初診日が障害年金で重要な理由
初診日は、どの年金制度で審査されるか、保険料納付要件を満たすか、いつの障害状態で認定するかを決める起点になるため、証明できないと請求が進めにくくなります。
初診日は単なる日付ではなく、審査の前提条件を決める起点です。初診日が動くと、請求できる年金の種類や、そもそも請求資格があるかまで変わります。
そのため審査側は、提出された診断書や申立書、添付資料が同じ初診日像を指しているかを重視します。ここが曖昧だと、医学的な重さ以前に、制度要件の土台が固まらず手続が止まりやすくなります。
受診状況等証明書が取れない場合でも、初診日を決めるロジックと証拠の積み上げ方を理解すれば、認定に近づけることは可能です。
初診日が確定すると決まること(加入制度・納付要件・障害認定日)
初診日が確定すると、まず「初診日に加入していた年金制度」が決まります。国民年金加入中なら障害基礎年金、厚生年金加入中なら障害厚生年金が中心になり、受け取れる年金の枠組みや加算の有無にも影響します。
次に、保険料納付要件の判定時点が初診日に固定されます。基本は初診日前の一定期間について保険料の納付や免除が適正であることが必要で、初診日が1日ずれるだけで要件の判定が変わる局面もあります。
さらに、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後、例外あり)の起算点になります。いつの障害状態で等級が判断されるか、遡及請求の可否や範囲にも関係するため、初診日未確定のままだと審査の土台そのものが定まりません。
受診状況等証明書が不要になるケース
原則は必要でも、請求の形や初診日の性質によっては、受診状況等証明書を別途添付しなくても初診日が扱える場合があります。
受診状況等証明書は原則として求められますが、必ずしも全員が同じ形で提出するわけではありません。先に「不要になり得るパターン」を押さえると、無駄な依頼や遠回りを減らせます。
ただし、不要かどうかは請求の状況と医療機関の組み合わせで変わるため、自己判断で省略すると手戻りになりがちです。診断書の初診日欄の記載根拠や、初診の扱いが制度上どう整理されるかを意識して確認します。
不要ケースに当てはまりそうでも、別の論点で証明が必要になることがあります。提出前に、初診日の定義が請求傷病と一致しているかまで含めて点検することが重要です。
先天性の障害など「生まれた日」が初診日となる場合
先天性の障害などで、医療機関への初回受診日を基準にせず「生まれた日」を初診日として扱う場面があります。この場合、初診医療機関の証明という発想より、出生時からの状態をどう示すかが中心になります。
立証は、母子手帳の記載、出生時の医療記録、乳幼児健診の記録、早期療育の記録など、時期が早い資料ほど説得力が出ます。医療機関のカルテが残っていない年齢帯でも、公的・準公的な記録を拾える余地があります。
ポイントは「いつから症状があったか」を生活歴の中で具体化することです。単に先天性と書くだけでなく、どの検査や健診で指摘されたのか、当時のフォロー内容は何かまで示すと、初診日の考え方がぶれにくくなります。
初診の医療機関で障害年金用の診断書を作成する場合
初診の医療機関が、そのまま障害年金用の診断書を作成する医療機関である場合、診断書の初診日欄の記載で足り、受診状況等証明書を別に求められないことがあります。
ただし注意点として、同じ病院でも診療科が異なる、紹介で受診したのが別科だった、途中で主傷病が整理され直したといった事情があると、初診の取り扱いが争点になりやすく、別途の確認資料が必要になることがあります。
また、診断書の初診日欄が「本人申告」ベースで記載されていると、証明力が弱く見られることがあります。病院側に記録根拠があるか、いつの記録に基づくのかを確認し、必要なら補強資料を用意しておくと安全です。
受診状況等証明書が取れない主な理由
取得不能の背景には、医療機関側の事情(閉院・記録廃棄等)や、受診経過(転院の繰り返し等)による情報断絶が多く、原因に応じた手当てが必要です。
取れない理由を曖昧にしたまま代替手段に進むと、後で「なぜ取れなかったのか」の説明が弱くなり、初診日全体の信用度が落ちます。まずは取得不能の原因を特定し、照会した事実を残すことが大切です。
医療機関側の事情と本人側の事情では、集めるべき資料が変わります。閉院や破棄なら残存記録の探索、転院を繰り返したなら次の医療機関の診療録に前医情報が残っていないか、という発想になります。
同じ「取れない」でも、手の打ち方は異なります。原因に合わせて、どのルートで証明を組み立てるかを早い段階で設計するのが、申請を前に進めるコツです。
廃院・カルテ破棄・転院で初診の記録が残っていないケース
廃院で連絡先が分からない、あるいは開設者が変わっていて記録の所在が追えないケースは珍しくありません。まずは医療機関名の変遷、医師会や保健所の情報、法人の引継ぎ先などを手がかりに、記録保管先がないか確認します。
カルテは保存期間の経過で破棄されていることがありますが、カルテがなくても会計データやレセプト関連の受診記録が残っている場合があります。ここに受診年月や診療科が残れば、初診時期の推定材料になります。
転院を重ねると、紹介状や検査結果が散逸しやすく、初診の情報が途切れます。この場合は、2番目以降の医療機関の初期記録に「いつ頃から、どこに通院していたか」が書かれていないかを探すのが、現実的な突破口になります。
一定期間に初診日があることを主張できるケース
日付の特定ができなくても、資料から「この期間内に初診がある」と確認でき、かつその期間中いつ初診日としても要件を満たすなら、推定的に初診日が認められることがあります。
初診日の証明は、必ずしも「この日」と1日まで確定できなければならないわけではありません。資料の組み合わせで「この期間のどこかで初診がある」と示せるなら、推定的に取り扱われる余地があります。
ただし、重要なのは期間の幅です。期間が広いほど、加入制度の切替や納付状況の変動が入り込みやすく、要件判定が不安定になります。できるだけ短い期間に絞り、期間設定の根拠が説明できる形にすることが肝心です。
この考え方は、単に主張すれば通るものではなく、制度要件に矛盾しないように組み立てる必要があります。期間を作る前に、年金記録と納付状況を確認するのが実務上の近道です。
「年月」まで分かる場合:その月の末日を初診日とする取り扱い
資料から「何年何月に受診した」までは分かるが日付が不明な場合、実務上はその月の末日を初診日として扱うことがあります。日を無理に作るのではなく、確定できる情報の範囲で処理する考え方です。
月が確定し得る資料としては、診療明細や領収書、受診月が分かるレセプト由来の記録、紹介状にある「○年○月頃受診」などが挙げられます。複数資料が同じ月を指していると、推定の精度が上がります。
注意点は、その月の末日に置いたときに、納付要件や制度加入の判定が不利にならないかです。同じ月でも初旬と末日では結果が変わるケースがあるため、月が確定した時点で要件との関係も同時に確認します。
「季節」しか分からない場合:季節末日を初診日とする取り扱い
「春頃」「夏頃」など季節表現しか残っていない場合、季節の終期日を初診日として扱う発想があります。季節は曖昧ですが、一定の期間として切り出しやすいという利点があります。
季節を支える資料は、単独では弱くなりがちです。学校の記録や勤務記録、手帳の申請時期、日記や家計簿、検査結果の時期など、生活上の出来事と医療受診を結びつける資料を組み合わせ、季節の範囲を狭めます。
季節推定では「なぜその季節と言えるのか」を説明できることが重要です。申立書には、症状が出たきっかけや通院開始の出来事を具体的に書き、資料と対応づけると、単なる記憶ではなく合理的な推定として伝わりやすくなります。
「年単位」しか分からない場合:始期終期の取り扱いで判断する
年しか分からない場合は、期間の始期と終期を資料で挟み込んで「一定期間内の初診」を組み立てます。つまり、ある時点では未発病だったと示す資料と、別の時点では受診していたと示す資料を並べ、その間に初診があることを論理的に示します。
始期に使いやすいのは、健康診断や人間ドックで異常所見がないことが確認できる記録、事故や発症の契機が明確な資料、医学的にその時期以前には発病しにくいと説明できる記録です。終期には、2番目以降の医療機関の受診記録、手帳申請の時期が分かる資料、給付申請時の診断書などが候補になります。
この方法の要点は、期間設定が広くなり過ぎないようにすることです。年単位のままだと審査の前提が揺らぐため、可能なら「年の前半」「転職前後」など追加情報で絞り込み、資料の言い方と合わせて期間の筋を通します。
この取り扱いが使えない注意ケース(納付要件の空白・年金制度の混在など)
一定期間内の初診が認められるためには、その期間中のどの日を初診日にしても、保険料納付要件を満たす必要があります。期間の途中に未納期間があると、初診日をどこに置くかで結論が変わってしまい、この取り扱いが使いにくくなります。
また、期間中に国民年金と厚生年金の加入が頻繁に切り替わっている場合も注意が必要です。どの制度で審査されるかが初診日に連動するため、期間設定が粗いと請求類型そのものがぶれ、追加資料の指示や差戻しにつながりやすくなります。
対策として、先に年金記録を確認し、納付状況の空白や加入制度の変化点を把握した上で、初診期間の候補を設定します。期間が要件の弱点に触れるなら、期間をさらに絞るか、別ルートの証明(次の医療機関記録など)を優先する判断が必要です。
受診状況等証明書が取れないときの代替手段
初診医療機関からの証明が取れなくても、次善の証明ルート(次の医療機関の記録、申立書、周辺資料)を組み合わせることで、初診日認定を目指せます。
代替手段は、単発の書類で置き換えるというより、複数の材料で同じ結論を支える作業です。審査側が知りたいのは、初診日そのものだけでなく、その日付が妥当だと判断できる根拠の積み上げです。
基本戦略は、1つ目の医療機関がだめなら2つ目、2つ目がだめなら3つ目というように、より上流の情報が残っていそうな記録を探索することです。それと並行して、取れない事情を正式に説明し、推定に使える資料を集めます。
ここで重要なのは、申立書の中身と添付資料の一致です。資料が示す範囲で主張を組み立て、言い切れない部分は不明として整理するほうが、結果的に信用度が上がります。
2番目以降の医療機関に証明書作成を依頼する
転院先のカルテや初診時の問診票、診療録には、前医名や受診時期が書かれていることがあります。特に転院直後の記録は、当時の情報が混ざりにくく、初診日推定の核になりやすいです。
前医情報が確認できたら、その医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼することを検討します。ポイントは、何を根拠に前医情報を記載できるかを医療機関側に確認し、可能なら診療録の該当記載があることを前提に作成してもらうことです。
記載の評価は、古い時期に作られた記録ほど強くなりやすい一方、近年の受診時にまとめて聞き取った内容だと本人申告色が濃くなります。その場合は、お薬手帳や領収書など別の資料で補強し、単独依存を避けると安定します。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成・提出する
受診状況等証明書が提出できないときは、その理由を公式に説明するための申立書を作成します。これは不足を埋めるための言い訳ではなく、審査が推定に入るための前提事情を整える重要書類です。
申立書には、廃院やカルテ破棄の回答内容、照会した日時や方法、誰に確認したかなど、取ろうとした経緯を具体的に書きます。結果だけでなく過程が書けると、取得不能が客観的に伝わります。
また、初診日をどう推定したのかの道筋も併記します。資料がある部分は資料に乗せ、資料がない部分は不明として整理するほうが、後で他書類と矛盾しにくくなります。
初診日を裏づける資料を集める(紹介状・診療明細・お薬手帳など)
初診日推定の資料は、医療記録だけに限りません。紹介状、診療明細、領収書、診察券、お薬手帳は、受診時期や診療科が分かることが多く、手元に残りやすい代表例です。
公的・準公的資料も有力です。健康診断結果、健康保険の給付記録、労災や自賠責などの申請書類、障害者手帳の申請記録や当時の診断書などは、時期の特定や期間の挟み込みに使えます。
集めるときの観点は、単に「通院していた証拠」ではなく、「初診時期を推定できる情報が入っているか」です。日付、年月、医療機関名、診療科、傷病名や主訴のどれが書かれているかを確認し、使える情報を整理していきます。
申立書の書き方のポイント(時系列・病院名・受診目的・根拠資料)
申立書は時系列が命です。いつ頃からどんな症状が出て、どこを受診し、どこへ転院し、いつ頃から継続受診になったかを、抜けと飛びを減らして並べます。思い出せない箇所は空欄にせず「不明」と書き、推測と事実を分けます。
医療機関名は正式名称が望ましく、所在地、診療科、受診目的も具体化します。同じ病院でも内科と精神科など科が違うと初診の扱いが変わることがあるため、科まで書く意義は大きいです。
根拠資料がある主張は、資料名と該当箇所を紐づけます。例えば「2016年7月受診」はお薬手帳の処方開始月や領収書で示し、「2016年春頃から不眠」は勤務記録や日記の記載で補強する、といった形にすると、申立てが検証可能な文章になります。
次の章では「提出前に確認したいチェックポイント」と題し、初診日の主張に関してチェックすべき点をまとめます。一方で、チェックポイントを細かく見て、ぬけもれなく対応を進めていくのは中々骨が折れる作業です。
ご相談いただき、一緒に対応を進めた例も多くございますので、まずは以下よりメールにてご相談をいただけますと幸いです。
提出前に確認したいチェックポイント
初診日の主張は、診断書や病歴就労状況等申立書、添付資料の記載と食い違うと大きな減点要因になるため、提出前の整合性確認が不可欠です。
初診日周りのミスで多いのは、書類ごとに表現がずれていることです。本人の記憶、医師の聞き取り、手元資料の年月がそれぞれ微妙に違うと、全体として信用度が下がりやすくなります。
提出前に一度、初診日候補を中心にして、発病時期、初めて受診した時期、転院時期、症状の悪化時期を並べ、矛盾がないかを確認します。整合性が取れていれば、日付が推定でも「筋が通っている」状態になります。
逆に、矛盾が残ったままだと、追加照会や再提出になりやすく、認定までの時間が伸びます。提出前のチェックは、結果に直結する作業です。
初診日の整合性(診断書・病歴就労状況等申立書・添付資料)
診断書には初診日、発病時期、治療経過が書かれ、病歴就労状況等申立書には通院歴と就労状況が書かれます。さらに添付資料には受診日や受診月が散らばっているため、同じ出来事を指しているか突合する必要があります。
実務のコツは、日付の粒度をそろえることです。日付まで確定できないなら、すべてを「年月」表記に統一し、資料で確定できる範囲から外れた言い切りを避けます。逆に、資料で日付が出ているなら、他書類もその日付に合わせます。
矛盾が見つかった場合は、まず医療機関に記載根拠の確認をし、修正が難しければ申立書で補足説明します。例えば「診断書は本人申告で2015年頃、資料では2016年7月の受診が確認できるため、初診月は2016年7月として主張する」など、ズレの理由と採用した根拠を明示すると整理がつきます。
まとめ|受診状況等証明書がなくても初診日を認めてもらう進め方
受診状況等証明書が取れない場合でも、次の医療機関の記録探索、申立書の作成、裏づけ資料の収集、そして「一定期間内の初診」構成を組み合わせることで、初診日認定の可能性を高められます。
最初にやるべきことは、受診状況等証明書が本当に取れないのかを確認し、取れないなら取れない理由と照会経緯を記録することです。次に、2番目以降の医療機関の初期記録に前医情報が残っていないかを探し、見つかれば証明書作成のルートに乗せます。
日付が確定しない場合は、月まで分かるなら月末、季節なら季節末、年単位なら始期終期で挟み込み、一定期間内の初診として筋の通る形に整えます。その際、期間中のどこを初診日にしても納付要件と加入制度の判定が崩れないかを必ず確認します。
最後に、診断書・申立書・添付資料の初診日関連の記載が同じストーリーになっているかを点検します。証拠の範囲で無理なく主張を組み立てることが、受診状況等証明書がなくても初診日を認めてもらうための最短ルートです。
「受診状況等証明書が取れないときの初診日証明|「一定期間に初診日があること」で認めてもらう方法」の関連記事はこちら
- 病院が閉院していたらどうする?受診状況証明書が取れないときの対処法
- 審査請求不支給での初診日証明書類の利用申出書の使い方
- 障害年金請求を有利に進める受診状況等証明書のチェックポイント
- 受診状況等証明書が取れないときの初診日証明|「一定期間に初診日があること」で認めてもらう方法
- 障害年金申請と学生納付特例制度の納付確認ポイントを総合的に理解する
- 国民年金保険料の法定免除制度について
- 障害年金申請のために知っておきたい国民年金保険料の「保険料免除」「納付猶予」「学生納付特例」納付時期を徹底解説
- 障害年金申請における保険料納付要件(3分の2要件・直近1年要件)を徹底解説
- 『初診日』が国民年金だった人が押さえておくべき3つの重要ポイント
- 20歳前傷病で障害年金をもらうときの手順と重要なポイント
- 障害年金の支給開始時期と手続きの流れを徹底解説
- 障害年金と社会的治癒とは?初診日が変わる仕組みと認定のポイント
- 障害年金の第三者証明をわかりやすく解説──初診日が証明できないときの対処法とは
- 障害年金不支給決定を覆すポイント―まず押さえておきたい基礎知識
- 障害年金の再申請請求を認めてもらえるポイントを徹底解説
- 障害年金が65歳以降でも申請できるケースとは?
- 障害年金の公的保険料の納付要件を確認するポイント
- 障害者手帳(3種類)を徹底解説:基礎から申請手続き・活用術まで
- 障害年金の更新(障害状態確認届)とは?手続きの流れと留意点を徹底解説




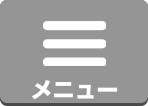
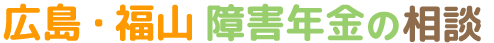
 0120-451-640
0120-451-640