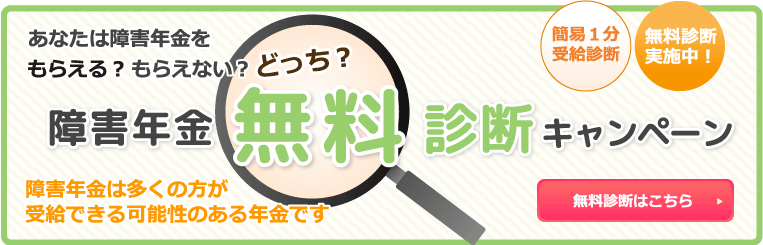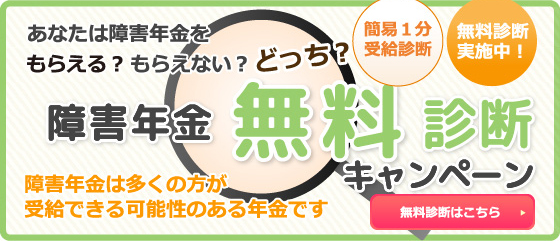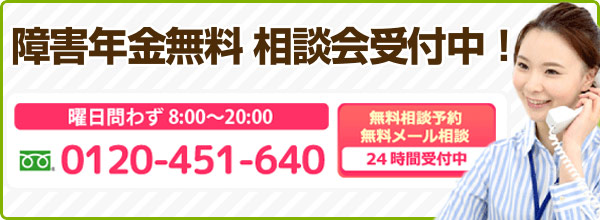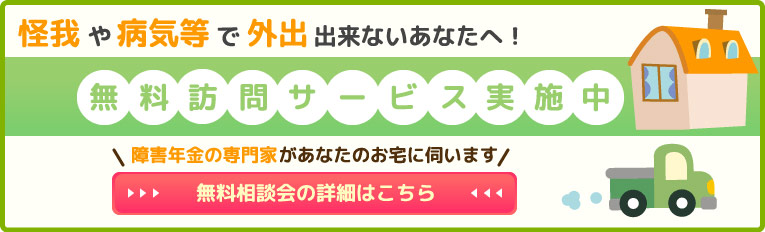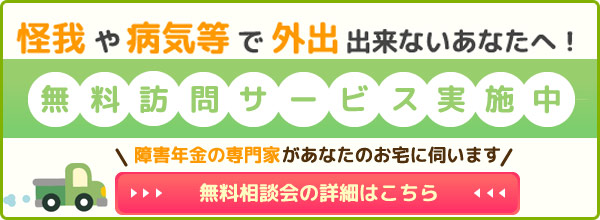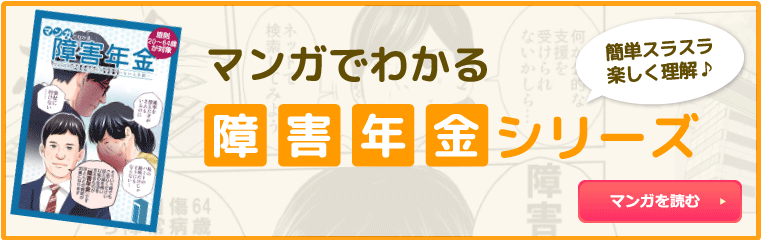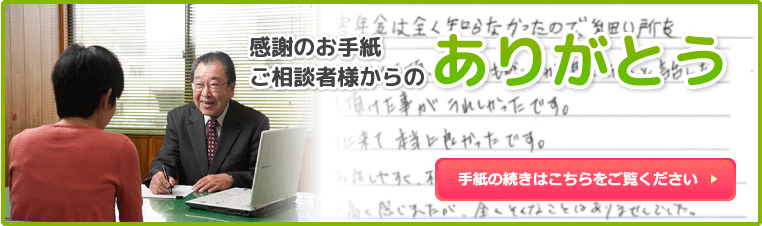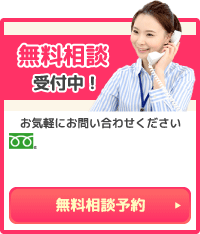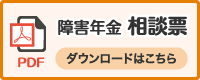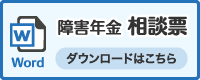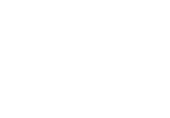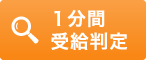障害者手帳(3種類)を徹底解説:基礎から申請手続き・活用術まで
障害の種類や程度により交付される障害者手帳には、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があります。
それぞれの手帳には対象とする障害や支援制度が異なり、申請方法や更新のタイミングも変わってきます。
この記事では、障害者手帳の基本的な仕組みから具体的な申請手続き、取得後に得られるメリット・デメリットまでを幅広く解説します。
自分に合った手帳を正しく取得し、日常生活のサポートを上手に活用しましょう。
障害者手帳とは?基本概念と意義
まずは障害者手帳の基本的な役割や意義について確認してみましょう。
障害者手帳とは、障害がある方が公的支援を受ける際の証明書として機能するものです。
障害の種類や程度を示すため、行政や福祉サービスを利用するときに必要となることが多いです。
加えて、割引や減免などの経済的メリットを受けやすくするための公式な証明手段としても広く活用されています。
手帳を持っていることで、就労支援や医療費助成など多岐にわたる支援を受けやすくなります。
一方、申請には医師の診断書や自治体の審査が伴い、人によっては負担を感じる場合もあるでしょう。
正しく取得し、適切に活用することで、生活の質を向上させる大きな手がかりになります。
また、障害者手帳は個人情報の一部を含むため、プライバシー面で注意が必要です。
安心してサービスを利用しつつ、自分の状況を的確に証明するうえでも、手帳の意義はとても大きいと言えます。
まずは手帳の仕組みを理解し、自分にとって最適な選択を目指すことが大切です。
3種類の障害者手帳の特徴
障害者手帳には3種類あり、それぞれ対象と支援内容が異なります。
身体障害者手帳は、視覚や聴覚、肢体等に何らかの障害を抱える方が対象で、健康面や日常生活への影響度に応じて複数の等級があります。
一方、精神障害者保健福祉手帳は、うつ病や統合失調症、発達障害など主に精神機能面でのサポートが必要な方を対象とし、こちらも等級が定められています。
さらに、療育手帳は知的障害を対象にした手帳で、自治体ごとに名称や区分が異なる場合があります。
障害の種類は多岐にわたりますが、手帳を取得しておくと日常生活の介助や医療費助成など、さまざまな公的サービスを受けるきっかけづくりになるでしょう。
手帳の存在は社会的な理解の促進にもつながり、自立や就労へのステップをサポートします。
個々の障害特性に合わせて、必要な手帳を選ぶことが重要です。
ただし、各手帳によって必要となる書類や判定の基準などが異なります。
そのため、自分自身の障害の特性や暮らし方を考慮したうえで申請に臨むと、スムーズに手続きを進めやすくなります。
次のサブセクションで、それぞれの手帳が対象とする障害や特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。
身体障害者手帳:対象と特徴
身体障害者手帳は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由、心臓や腎臓などの内部障害といった身体機能面の障害を持つ方に交付されます。
障害の程度に応じて1級から6級(自治体によっては7級まで含む場合もあり)の等級に分けられ、等級が重いほど受けられる支援が手厚くなる傾向があります。
具体的には、医療費の補助や公共料金の減免、公共交通機関の優先席利用など、生活面に関わる制度が含まれます。
精神障害者保健福祉手帳:対象と特徴
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症やうつ病、発達障害、高次脳機能障害など、精神面で継続的なサポートが必要な方が対象となります。
等級は1級から3級まで設定されており、等級によって自治体の福祉サービスや就労支援の内容に違いがあるのが特徴です。
有効期限が設定されており、定期的に更新の手続きを行いつつ、社会生活における生きづらさを緩和するサポートを受けることが可能です。
療育手帳:対象と特徴
療育手帳は、知的障害を持つ方が対象となり、自治体によって名称や手帳のデザインが異なる場合があります。
一般的にA判定(重度)とB判定(それ以外)に区分され、知能指数(IQ)や生活年齢、社会適応能力などの総合評価に基づいて判定されます。
支援内容は就学時のサポートや福祉サービスの利用優先度が高まるなど多岐にわたり、知的障害者が安心して生活を送るために重要な役割を担っています。
障害者手帳の等級・有効期限を理解しよう
手帳の等級や有効期限は、支援内容や更新時期を理解するうえで重要なポイントです。
障害者手帳は、障害の程度を等級という形で区分し、それがサービスや支援の内容を決定する材料になっています。
また、有効期限が設けられている場合があり、期限を過ぎると更新手続きを行わない限り、支援が滞ってしまう可能性があります。
自身が持つ障害者手帳の等級や有効期限を把握しておくことは、必要な助成や制度を安定的に受けられるためにも大切です。
等級や有効期限の設定は、障害によって変化する症状や状態を踏まえたうえで見直しを行うことを意図しています。
特に、身体障害では症状の変化が少なくても、更新時の診断書提出が必要な場合があるなど、手続き上の注意点が多々あります。
計画的に準備を進めることで手続きの煩雑さを減らし、期限切れによる不利益を回避できるでしょう。
自治体によって提出書類や申請の流れが若干異なることもあります。
仮に手帳を取得した後で症状が改善したり、逆に進行したりした場合は、等級の見直しや再申請が必要となるケースがあるため、医療機関や担当窓口との連携が欠かせません。
次のサブセクションでは、具体的な等級や更新の流れをまとめていきます。
身体障害者手帳の等級と更新の流れ
身体障害者手帳では1級から6級までの等級が設けられ、視覚・聴覚・肢体・内部障害などそれぞれの障害特性に応じて判定が進められます。
更新時には医師の診断書を提出する必要があるため、病院での検査や書類準備が欠かせません。
症状に大きな変化がない場合でも、手帳自体に記載された期限が来る前に必要書類を整えて自治体に提出することで、サービスの継続性を確保できます。
精神障害者保健福祉手帳の等級と有効期限
精神障害者保健福祉手帳は1~3級で判定され、有効期限が2年に定められているのが特徴です。
基本的には2年ごとに更新手続きを行う必要があるので、通院状況や主治医の診断書をあらためて用意し、行政の審査を受けます。
更新を怠ると手帳の効力が失われ、医療費助成や就労支援の優遇措置などが受けられなくなる恐れがあるため、期限管理に注意しましょう。
療育手帳の区分と再判定のタイミング
療育手帳では自治体ごとにA・Bなどの区分が設定され、定期的な再判定が行われる場合があります。
子どもの年齢や成長度合いに応じて知能検査や心理判定を再度受けることで、区分が変更になることも考えられます。
障害の状態が変化したときは早めに再判定を受けることで、より適切な支援やサービスを確保できます。
障害者手帳の対象となる障害例
各手帳に該当する具体的な障害例を押さえておきましょう。
障害者手帳は、いずれの種類も幅広い障害をカバーしていますが、制度上の「対象障害」には明確な基準が設けられています。
該当しそうな症状や疾患は、実際に医療機関に相談することで正式な診断に基づいた判定が得られます。
対象障害の具体例を知っておくと、自分や家族、あるいは身近な方がサポートを必要とする際に役立つでしょう。
しかし、障害の状態は人によって異なるため、一律に手帳を取得できるとは限りません。
医師の診断のみではなく、自治体が実施する判定を経てようやく正式に手帳が交付されるため、調整や手続きに時間がかかることもあります。
該当の可能性がある場合は、なるべく早めに情報収集を行い、必要書類などを準備することが大切です。
以下のサブセクションでは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳がそれぞれ主に想定している障害の例を簡単にまとめます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、適切な手続きを進める参考にしてください。
身体障害者手帳が対象とする主な障害
身体障害者手帳では、視覚障害(視力低下や視野狭窄など)、聴覚障害(難聴や平衡機能障害など)、肢体不自由(上肢・下肢・体幹の機能障害)、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器などの機能障害)などが代表的な対象となります。
これらの障害は、日常生活や社会参加に大きな困難をもたらす可能性があるため、適切な支援を受けられるよう早めに申請を検討することが望ましいでしょう。
精神障害者保健福祉手帳が対象とする主な障害
精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患には、統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、高次脳機能障害などが含まれます。
症状の程度や社会生活への影響度合いを踏まえて等級が決定されますので、病気の状態や治療経過は手帳申請の際に重要な情報となります。
通院歴なども審査で考慮されるため、主治医とよく相談しつつ手続きに臨むとスムーズに進められます。
療育手帳の対象となる障害の具体例
療育手帳は、知能指数(IQ)が一定の基準を下回る場合や、社会適応能力に著しい制限がある方が対象です。
先天的または後天的な要因で知的障害が生じている場合も対象となり、発育年齢が遅れている子どもを持つ保護者にとっては重要な手帳と言えます。
年齢や成長度合いによって判定基準が異なるため、お住まいの自治体の担当窓口で詳しい情報を確認してください。
障害者手帳のメリット・デメリット
手帳を取得するメリットと、場合によっては生じるデメリットを理解しましょう。
障害者手帳を持つことで得られるメリットとして、医療費の自己負担軽減や各種料金・税金の減免、公共交通機関やレジャー施設での割引などが挙げられます。
特に医療費助成は長期的な治療やリハビリが必要な方にとって大きなサポートとなるでしょう。
これらの優遇措置は、障害を抱える方が経済的にも社会的にも自立しやすくする背中押しの役割を担っています。
就労面でも、障害者雇用枠へ応募が可能になり、採用後には合理的配慮や職場環境の整備といった支援を受けられる場合が多いです。
特に重度認定の場合には企業の雇用率算定で優遇されることがあるため、就職先探しの際に手助けとなることがあります。
一方で、手帳を取得する際に医師の診断内容が必要となるため、自分の障害を公的にも証明する形となる点には抵抗を感じる方もいるかもしれません。
また、手帳の所持が周囲に知られることでプライバシーの問題が生じる可能性も考えられます。
職場や学校で手帳を見せる場面では、障害の開示に伴う心理的なハードルもあるでしょう。
ただし、適切な開示と制度利用ができれば、日常生活や社会参加を大きくサポートする存在になるため、デメリットとのバランスを取る工夫が求められます。
メリット:税金・料金面の割引と福祉サービス
障害者手帳を提示することで、医療費の助成や医療保険自己負担軽減、公共施設利用料の割引、住民税や所得税などの減税制度を利用できる場合があります。
これらの支援が適用される範囲は自治体や障害の程度によって異なりますが、生活コストの負担を大きく軽減できるのが魅力です。
福祉サービスとも連携しており、必要に応じてヘルパー派遣や介護保険サービスなども利用しやすくなります。
メリット:就労や社員支援制度の拡充
手帳所持者は法定雇用率に基づき企業が積極的に採用を行う制度を利用でき、採用後は職務上の特別配慮や合理的配慮を受けられる可能性があります。
休憩時間や作業量の柔軟対応、仕事環境の改善など、障害特性に合わせて働きやすい環境が整備されることも多いです。
こうした仕組みがあることで、自分に合った働き方を見つけやすくなり、長期的なキャリア形成に発展することが期待できます。
デメリット:プライバシーと手続きの負担
手帳を取得するためには医師の診断書や各種書類の用意など、少なからず手間と時間がかかります。
その過程で自分の障害を公的に証明することに抵抗を持つ方もいるでしょう。
また、職場や周囲に手帳の存在を知られることで、偏見を受けたり、個人情報が広まったりするリスクもゼロではありません。
こうしたデメリットを踏まえながらも、必要な支援を得るために手帳取得を検討する価値は大いにあると言えます。
障害者手帳を取得すると受けられる主な支援制度
手帳所持者が活用できる支援やサービスについて紹介します。
障害者手帳があることで受けられるサポートは多岐にわたります。
医療費の助成だけでなく、日常生活に欠かせない福祉用具の導入支援や通所施設の利用など、個々の障害の状況に合ったサービスを利用できる可能性があります。
さらに、家族への支援や介護者へのサポート体制が整っている自治体も少なくありません。
また、交通やレジャー施設など、娯楽・外出に関する優待サービスを活用できるのもメリットです。
生活の質を高める意味でも、移動のしやすさや心理的な負担軽減につながるでしょう。
これらの制度をアクティブに取り入れることで、より豊かな日常生活を送りやすくなります。
支援制度は日々アップデートされている場合もあるため、最新情報を常にチェックすることが重要です。
お住まいの自治体や利用を考えているサービスの公式サイトなどを参考にしながら、自分の状態に合った制度を上手に使いこなしましょう。
医療費助成・補装具支援
障害者手帳を取得すると、保険診療分の自己負担が軽減される医療費助成制度を利用できることがあります。
また、補装具や福祉用具の購入費を公的に支援する制度もあり、車いすや補聴器などの負担が大きい用品でも自己負担額を抑えて導入できる可能性があります。
これらの支援は自治体ごとに異なるため、詳細は地域の福祉窓口で確認するとよいでしょう。
交通機関やレジャー施設等の割引
公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)や航空機、フェリーなどで割引が適用されるケースがあります。
また、レジャー施設や映画館、博物館、美術館などでも障害者手帳を提示することで入場料が優遇されることがあるため、趣味や余暇を楽しむ際の負担軽減に役立ちます。
こうしたサービスを活用することで外出のハードルが下がり、社会参加を一層充実させるきっかけとなるでしょう。
特別児童扶養手当などの経済的支援
障害を抱える子どもがいる家庭では、特別児童扶養手当などの給付を受けることで、経済的な負担を軽減できる場合があります。
さらに、条件を満たせば障害年金の受給対象になる可能性もあり、生活費や医療費の確保に大きく寄与するでしょう。
これらの手当は障害の程度・家族構成・収入状況など、さまざまな要件を総合的に検討して決定されるため、該当しそうな場合は早急に申請情報を確認することが重要です。
障害者手帳の申請手続きと必要書類
各手帳の申請方法や必要書類を押さえておくと、スムーズに手続きを進められます。
障害者手帳の申請は、いずれの種類も自治体の担当窓口へ行うのが基本です。
必要な書類として一般的には医師の診断書、申請書、場合によっては写真や本人確認書類などが挙げられます。
実際の手続きは自治体ごとに微妙に異なるため、まずは市区町村の福祉課や保健福祉センターなどに相談することが第一歩です。
なお、手帳の申請にはある程度の時間がかかることが予想されます。
急いでいる場合でも審査プロセスは省略できないため、スケジュールに余裕をもって準備を進めるとよいでしょう。
書類の不備などがあると再提出が必要になることもあるため、早めの着手が成果につながります。
続いては、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳それぞれの手続きを個別に確認していきましょう。
書類の違いや注意点を把握することで、スムーズな取得を目指すことができます。
身体障害者手帳の申請:診断書と手続きの流れ
身体障害者手帳の場合、所定の用紙に医師の診断書を記入してもらう必要があります。
診断書の内容は障害部位や程度を詳細に記載するため、受診する前に自治体から指定された書類を取り寄せておくと良いでしょう。
診断書の提出後は自治体の審査を経て、手帳が交付されるまでに数週間から数か月ほどかかる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の申請:注意点と手順
精神障害者保健福祉手帳の申請では、指定医が作成した診断書を用意し、過去の通院期間や治療状況が一定期間以上であることが求められる場合があります。
診断書の有効期限も定められており、一般的には書類作成から3か月以内に申請を行う必要があるため、時期を逃さないよう注意が必要です。
申請後は自治体の判定を待ち、問題なければ手帳が交付されます。
療育手帳の申請:判定基準と書類の準備
療育手帳の申請では、心理判定や知能検査の結果をもとに知的障害の程度を判定します。
自治体によって検査の方式や実施場所が異なる場合があるため、事前に窓口に問い合わせてスケジュールを調整することが大切です。
必要な書類がそろうと審査に入り、判定結果が確定すると手帳が発行されます。
更新・再申請のポイント
期限がある手帳や障害状態が変化した場合の更新に関しては、早めに対策しておきましょう。
手帳の有効期限がある場合、期限が切れる前の数か月以内に更新手続きを行う必要があります。
特に精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が基本となっているので、通院スケジュールとあわせて計画を立てましょう。
身体障害者手帳や療育手帳でも、状況や自治体で異なる更新・再判定のタイミングがあるため、手帳交付時に確認しておくと安心です。
更新には新たに医師の診断書が必要となる場合が多く、診断書の内容によっては等級が変更されることもあります。
障害の進行や改善により、手帳なしでも生活が可能になるケースや、逆に支援を手厚く受ける必要が出てくるケースもあるでしょう。
状況が変わったら早めに担当部署と相談することが大切です。
時期を逃すと、せっかく取得した支援が受けられなくなる可能性があります。
煩雑に感じるかもしれませんが、継続的にサポートを受けるためには計画的な更新が欠かせません。
手帳の有効期限をカレンダーなどで管理し、必要な書類を早めに準備しておくとスムーズに再申請や更新を行えるでしょう。
更新手続きのタイミングと必要書類
更新手続きの時期は、手帳に記載の有効期限や自治体からの通知を目安に進めると良いでしょう。
必要書類は新しい診断書や申請用紙、写真などの場合が多く、特に診断書は準備に時間を要するので余裕を持った行動が肝心です。
期限を過ぎると、改めて新規申請が必要になることもあるため注意してください。
等級変更が生じるケース
障害の状態が変化した場合、再判定によって等級が上がったり下がったりすることがあります。
その結果、受けられる支援内容が変更になり、税金や施設利用の減免率が変わることもあるでしょう。
等級変更の際は、新たな診断書や審査が必要となるため、体調変化を感じたら担当医や行政窓口に早めに相談するのがおすすめです。
複数の障害者手帳を同時に持つことは可能?
複数の手帳が同一人物に交付されるケースと、そのメリット・課題を確認します。
身体障害と精神障害を併せ持つ方など、複数の障害要因が存在する場合は、それぞれの手帳を交付される可能性があります。
同時所持によって、双方の制度からサポートを受けられるメリットが高まり、医療費や就労支援、福祉機器の導入など多面的な支援を得やすくなるでしょう。
一方で、複数の手帳を管理する手間や更新手続きの負担が増えるという課題もあります。
各手帳ごとに異なる提出書類や期限管理が必要であり、医療機関とのやり取りも複雑化する可能性があります。
常に最新の情報を確保し、計画的に手続きに臨むことが大切です。
また、複数所持している重度障害の場合は、障害者雇用率でカウントが加算されるなどの特例があることも考えられます。
自分にとってどのような支援が必要か、あるいは手帳を所持するメリット・デメリットを総合的に判断したうえで申請、管理に取り組むことが望ましいでしょう。
手帳を複数所持する場合のメリット・デメリット
複数手帳の所持による最大のメリットは、障害特性に合わせた多角的な支援を得られる点です。
逆にデメリットとしては、手続きや更新にかかる書類準備の手間が増え、プライバシー管理が難しくなる可能性があります。
自分の生活全体を支えるために、必要なサポートがどの手帳から得られるのかを総合的に検討することが大切です。
障害者手帳に関するよくある質問
申請や活用において多くの人が抱える疑問点をまとめました。
手帳の申請が通らなかった場合や、診断書をどのタイミングで取得するべきかなど、実際の手続きには不明点が多いかもしれません。
ここでは、実際に寄せられやすい質問と基本的な対応策について取り上げます。
事前に知っておくとスムーズな手続きや問題解決に役立つでしょう。
また、手帳を取得してから等級の変更が通知された場合はどのように扱うのか、更新時に準備が間に合わない場合はどうするのか、といった疑問もよく耳にします。
こうした疑問は自治体の窓口だけでなく、医療機関や相談支援センターなどでも丁寧に答えてくれることが多いです。
疑問や不安な点があれば、ためらわずに専門機関へ問い合わせることが、手帳を有効に活用するコツでもあります。
次のサブセクションを参考にしながら、思い当たる疑問点をチェックしてみてください。
手帳申請が却下された場合の対応
もしも手帳申請が却下されたら、まず却下内容の理由を担当窓口に確認しましょう。
提出書類に不備があるのか、診断書の内容が基準を満たしていないのか、あるいは他の手帳の方が適切と判断されたのかなど、理由によって対応は異なります。
必要に応じて再申請や不服申し立ての制度を利用し、自分の受けられるサポートがきちんと確保できるように取り組むことが大切です。
申請時の診断書はどう取得する?
診断書の取得方法は、主治医やかかりつけ医に申し出て作成してもらうのが一般的です。
自治体によって指定書式が存在する場合があるため、事前に役所や福祉課のWEBサイトなどで書式をダウンロードし、医療機関に持参するとスムーズです。
医師に依頼した後、完成した診断書は有効期限内に自治体へ提出する必要があるため、受け取り時期をしっかり把握しましょう。
障害者手帳の等級が変わったらどうする?
等級が変わった場合は、手帳そのものや受けられる支援内容に変更が生じる可能性があります。
新しい診断書や手帳の再交付が必要になるため、自治体の担当窓口に早めに相談しましょう。
特に税金や福祉サービスの減免率は等級に連動しているケースが多いので、通知が届いた時点ですぐに手続きに移るのがおすすめです。
障害者手帳の代わりになるものはある?
場合によっては他の証明手段を検討することもあります。
障害者手帳を取得していない方でも、医療機関の診断書や通院履歴などで障害の状況を一時的に証明することは可能です。
ただし、手帳と同等の公的支援を受けるためには原則として手帳の所持が必要となる場合が多く、代わりとなるものは限定的です。
企業や学校によっては独自の配慮制度を設けていることがあるので、状況によっては手帳なしでも一定の支援を受けられるかもしれません。
医療保険の特例や介護保険サービスの一部を活用できる場合もありますが、制度の適用範囲は障害者手帳ほど広範ではありません。
さらに、障害者雇用枠に応募する際は手帳が証明書として求められるケースが多いため、長期的な社会参加や安定的な支援を考えるのであれば、やはり手帳の取得を検討することが望ましいでしょう。
一部の自治体では独自のサポートや配慮制度を進めている場合もあるため、手帳がなくても利用できる福祉制度がないかこまめに情報を集めると良いかもしれません。
とはいえ、公的保証を幅広く活用するためには手帳の交付が最も確実な方法となることが一般的です。
まとめ:自分に合った手帳を取得し、充実した日常を目指そう
最適な手帳を取得して、豊かな生活を送るためのポイントを振り返りましょう。
障害者手帳は、大きく分けて身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類が存在し、それぞれが異なる障害特性に対応した制度を提供しています。
手帳の等級や有効期限を正しく把握し、期限前に更新や再判定を受けることで、継続的な支援を得やすくなるでしょう。
医療費の助成や就労支援、各種割引などのメリットがある一方、プライバシー面や手続きの負担といったデメリットも存在します。
自分の生活や将来の展望を見据え、どのようなサポートが必要かを考えながら申請することが大切です。
必要があれば複数の手帳を併せて活用し、より充実したサポートを受けられる体制を整えるのも一つの選択肢です。
最後に、申請や更新のプロセスで困ったことや不明点があれば、医療機関や自治体の窓口、地域の相談支援センターが頼りになります。
正しい情報を基に行動し、自分に合った障害者手帳を取得して、日常生活をより快適かつ豊かにする一歩を踏み出しましょう。
「障害者手帳(3種類)を徹底解説:基礎から申請手続き・活用術まで」の関連記事はこちら
- 障害年金申請と学生納付特例制度の納付確認ポイントを総合的に理解する
- 国民年金保険料の法定免除制度について
- 障害年金申請のために知っておきたい国民年金保険料の「保険料免除」「納付猶予」「学生納付特例」納付時期を徹底解説
- 障害年金申請における保険料納付要件(3分の2要件・直近1年要件)を徹底解説
- 『初診日』が国民年金だった人が押さえておくべき3つの重要ポイント
- 20歳前傷病で障害年金をもらうときの手順と重要なポイント
- 障害年金の支給開始時期と手続きの流れを徹底解説
- 障害年金と社会的治癒とは?初診日が変わる仕組みと認定のポイント
- 障害年金の第三者証明をわかりやすく解説──初診日が証明できないときの対処法とは
- 障害年金不支給決定を覆すポイント―まず押さえておきたい基礎知識
- 障害年金の再申請請求を認めてもらえるポイントを徹底解説
- 障害年金が65歳以降でも申請できるケースとは?
- 障害年金の公的保険料の納付要件を確認するポイント
- 障害者手帳(3種類)を徹底解説:基礎から申請手続き・活用術まで
- 障害年金の更新(障害状態確認届)とは?手続きの流れと留意点を徹底解説




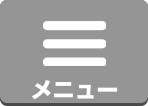
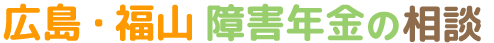
 0120-451-640
0120-451-640